日付: 2025年 2月 13日
形式: ビデオインタビュー(日本語)
進行: Lee Hansu
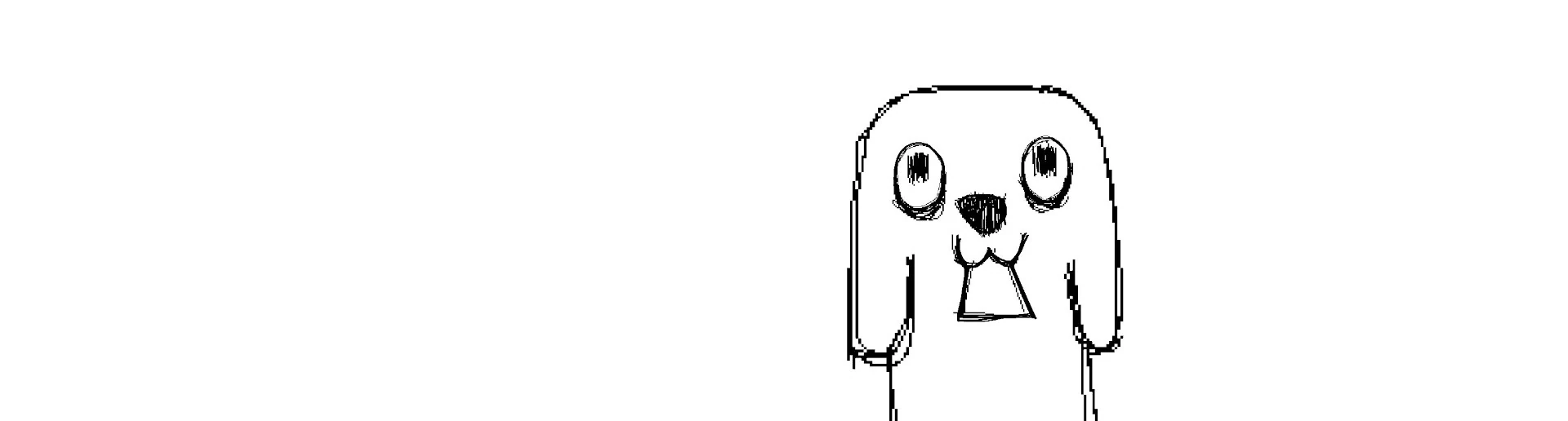 lilbesh ramko
lilbesh ramko
まず、自己紹介お願いします。
lilbesh ramko(offline)新生nanachi.xp/MiAε錬成.+22%yunwii ramko(nw) という名前で活動しています。普段はサウンドクラウドを中心に、大きい音の音楽を作っています。
呼び名は「ラムコさん」でよろしいでしょうか。
はい、ラムコで大丈夫です。(笑)
ありがとうございます。では、lilbesh ramko という名前の由来について伺えますか。
もともと、lil wayne や lil peep が好きで「lil」を付けたいと思ったんですよ。それから、「besh」はうちで飼っている猫の名前なんです。その猫の名前を組み合わせて「lilbesh」になりました。
「ramko」の方は、自分の好きなアニメ・漫画『ゆるゆり』のキャラクターである歳納京子(としのうきょうこ)が、作中で漫画家として活動する際のペンネームが西京極ラム子(にしきょうごくらむこ)っていうんです。そこから取って「lilbesh ramko」になりました。
単純にそのキャラクターが好きで「ramko」になったのでしょうか。
『ゆるゆり』はもともと好きでしたんですけど、アーティスト名をどうしようかと悩んでいたときに『ゆるゆり』を観て、一番好きなキャラである歳納京子ちゃんのペンネームの響きが可愛いかったので、すごいいいなと思ってそこからとりました。
「lilbesh」は子猫の名前、「ramko」はアニメのキャラ由来で、キュートな感じですね。
そうですね。
ヒップホップカルチャー意識で「lil」を付けたと先言ってくださった通り、サウンドクラウドの初期作品はトラップやクラウドラップ系ですね。それが今のハイパーポップ、デジコア色彩になったきっかけを教えてください。
ハイパーポップやデジコアと呼ばれる音楽には2020年頃から出会いました。その時期からずっと聴いていたんですが、しっかり意識して作ろうと思うようになったきっかけは osquinn(元: quinn, p4rkr)というアーティストとの出会いでした。彼女の曲が自分の音楽に影響を与えています。
以前 100 gecs の影響について触れていたインタビューを拝見したこともありまして、lilbesh ramko = ハイパーポップ・デジコア系アーティストという印象がありますね。同時に、日本のインディーズの、例えば moreru や春ねむりさんみたいなノイズ・ハードコア・ファンクの影響も受けているのでは?と思ったのですが、いかがでしょう。
自分が活動を始めた後で、そっち系も好きになったんですが、直接の影響はあまりないです。いちばん大きいのはやはり 100 gecs とか、フランスの Justice ってバンドですね。Justice の音楽は音が割れてるっていうか、昔からディストーションをすごい採用していた曲が多かったので、その音作りとかにすごい影響されました。

pitchfork で、hirihiri さんとのフィーチャリングによるピーナッツくんの「Wha U Takin Bout」が高評価されたことがありました。確かにお2人の相性がいいと思います。2人で「142clawz」というチーム活動もされてますね。どのような活動なのでしょうか。
142clawz は2022年の夏前、7月くらいに hirihiri さんと出会って5曲ぐらいを一気に作り上げたことがありまして、そのEPを2人で作ってから「すごい楽しいね」みたいな話になったことがきっかけでした。その年に FORM 主催の『All Nighter』という、24時間で曲を作って応募するコンピレーションアルバム企画に hirihiri さんと2人で挑戦しました。そこに提出した曲「142clawz」がそのままチーム名になりました。 チーム名の由来としては、24時間で作らないといけないから、寝る時間を少なくするためモンスターエナジーっていうカフェインドリンクを飲んでたんです。そのカフェイン配合量が142gで、ロゴマークの爪から claws を付けて、そんな感じです。
EPは『IDK+LW RMXZ』のことですか。
いいえ、『10 MICROPHONES AND DISTORTED WAVEFORMS!!』ですね。
確かに、それならチーム活動せざるを得ないですね。(笑)最近リリースされた「SHIRANKEDO - 142clawz REMIX」もすごく良かったですが、どういう経緯で生まれた楽曲なのでしょうか。
ありがとうございます。あの曲はライブイベントで知り合った方から「「SHIRANKEDO」っていう曲のリミックスをしてみない?」とお誘いを頂いて、hirihiri さんと2人で制作した形になります。
その方は AVYSS のレーベル関係とかでしょうか。
いえ、違いますね。なんかいろいろやっていく人です。(笑)
偶然から生まれた作品なんですね。(笑)
そうですね。(笑)
ディスコグラフィを見ると、カナダの tennyson さん、今回同じライブ(『Azure Vol.1』)に出演する hallycore さんも思い浮かびますが、特にトップシークレットマンとのコラボが目立ちます。オリジナルナンバー「ヒミツ!!!!!」も神聖かまってちゃんをカバーした「死にたい季節」も印象深かったです。トップシークレットマンとの作業はいかがでしたか。
作詞、作曲をやっているボーカルのしのだ君と出会ったのが去年の2月くらいだったんですけど、出会ってすぐにお互いの音楽の趣味とかが意気投合して、曲を作りたいなって話になりました。
最初はスタジオに入ってしのだ君のギターリフを録ったりしたんですが、なかなか上手くいかずボツになって、最終的には自分が打ち込んだビートにしのだ君が乗ってもらう形になりましたね。
それが「ヒミツ!!!!!」。
はい。
「ヒミツ!!!!!」はラムコさんもボーカル参加していますよね。
そうです。とりあえず自分が声を録って送って、しのだ君がボーカルデータを返してくれたって感じです。
一緒に曲を作るとき、気にしているものがあったりしますか。特になくても大丈夫です。
なんだろうな。本当に、あまり無いですね。バイブスでって感じです。
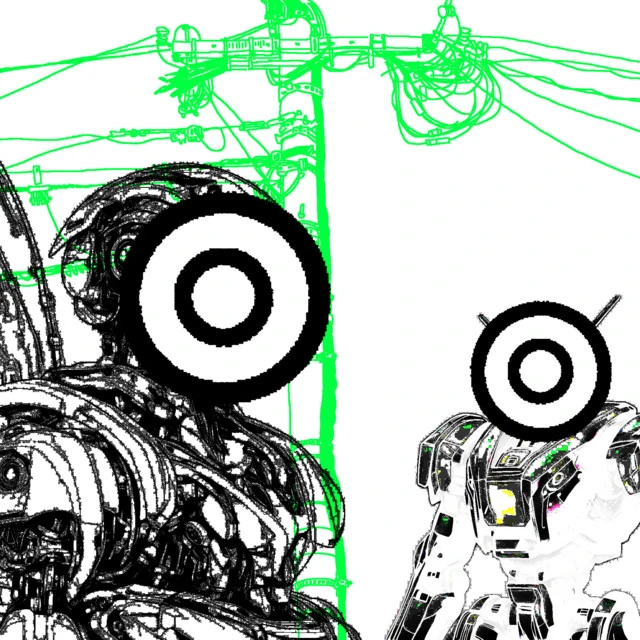
昨年9月にリリースされた『徘徊collection』について伺いたいと思います。終末から徘徊、曲もラブソングみたいになっていると思います。その変化について話をお聞きいただけますでしょうか。
『終末collection』は大きい意味で「世界の終わり」みたいなものを曲にしたつもりで、『徘徊collection』は世界の終わり後の「ポストアポカリプスの世界」をイメージして作った曲が多いです。『終末collection』よりも『徘徊collection』の方が多くの人に届けられるような音楽を作れた気がします。
『終末collection』は新型コロナウイルスの影響かなと思いましたが。
それは意外と考えずに作りました。その時期は精神的に不安定だったので、その時の気持ちだと「早く世界終わってほしい」みたいな。
分かります。(笑)
分かりますか。(笑)
『徘徊collection』は精神的に安定している意味にも見られるのでしょうか。
そうですね、落ち着いたじゃないけど、俯瞰して見れるようになったって意味も込められてて、終末後の世界を歩き回るって意味で「徘徊」って付けました。
では、ラムコさんの中で「ポストアポカリプスのイメージ」と「ラブ」の関係は何でしょうか。
人が住んでそうな場所って、誰かがいた痕跡みたいなのって、すごい「愛」じゃないですか。そこに人がいた痕跡に感じる温かみみたいな、そういうのが好きです。あまり具体的なテーマはないけど、無機質なものに感じる人の温かさみたいなのを意識したのかな。
歴史とか遺跡とかを見て「昔ここでこういう人がいたな」みたいな。
だいぶそんな感じです。(笑)
「nichijou:loopmania」と「うそつき」は先行リリースした曲でしたが、その2つの曲を先に完成し、それらを基にアルバム全体を作り上げたという流れでしょうか。
はい、そうです。
ポストアポカリプスのイメージも「nichijou:loopmania」や「うそつき」と同時に生まれたのでしょうか。
そうですね、「nichijou:loopmania」を作った時ぐらいからそういう構想があって、「生活に焦点を当てたいな」って。それで「うそつき」みたいな曲が生まれた感じでした。
最後のトラック名が「haikai:pop」となっていて、それが最初だったかなと思いました。
元々全部同時進行だったんですけど、「nichijou:loopmania」の後にできたのが「うそつき」で、その後にできたのが確か「haikai:pop」だった気がします。
「re:kazing (feat. AssToro)」のメロディーについて伺いたいです。ラムコさんのボーカルスタイルと、このエモーショナルなメロディラインの組み合わせが新鮮でしたが、もう少し詳しく教えていただけますか。
ありがとうございます。「re:kazing」の感じは「nichijou:loopmania」のすぐ後に作り始めたんですよ。なので、「nichijou:loopmania」のメロディーと似てるかも知れないです。
「うそつき」と「ヒミツ!!!!!」のドロップ区間では耳が詰まるような圧迫感を感じます。同時に打撃感があってライブ感を感じられます。パッドやコンプレッサーなどを使っていますか。
ドラムのパターンとベースは全部 MIDI で作っています。それと全体的にディストーションをかけて大音量を作っています。
「ヒミツ!!!!!」のサビはリズムが三三七拍子になっていて応援歌にも聞こえてきます。Netflix の『イカゲーム』の「Way Back then」とも共通点があって面白かったです。この曲についてもう少し詳しく教えてもらえますでしょうか。
サビのメロディーが三三七拍子って気づいてくれてすごい嬉しいです。元々あの曲はあのドラムパターンではなく、三三七拍子の曲にするつもりだったんですよ。三三七拍子の曲に作れたけど、ドラムパターンを結局変えて、あのメロディーになりました。
歌詞も「あの子の秘密が知りたい」という可愛さを感じられますが、実際に「秘密が知りたい人」がいたりしますか。
沢山います。(笑)トップシークレットマンと作った曲なので、シークレット感を出したかったです。
「haikai:pop」はボーカロイド系にも似てる印象があります。日本の電子音楽シーンはボーカロイドシーンとも関係がありますよね。今後、ボーカロイドを使った曲も考えたりしますか。
そうですね、ずっと作りたい気持ちはあります。もともとボーカロイドの曲は好きだったんですが、「haikai:pop」はそういう曲をめちゃめちゃ聞いてた時期にできたこともあります。途中の機械音声パートも、その影響かもしれないですね。

ライブの話へ移りたいと思います。曲作りから自主企画の『バビフェス』というライブの開催まですごい DIY 精神ですね。苦労はありませんか。
そうですね、でもあまりわからないかもしれないです。只々「楽しいことしよう」って気持ちで、ノリというか、バイブスで生きてきているので。なるべく嫌なこと考えずに「楽しいことしよう」と思ったら今の感じになりました。
「楽しいこと」を優先していくことは素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
今年は日本でのツアー、そして2月22日には韓国公演『Azure Vol.1』が予定されています。その急成長の背景には、音源では味わえないライブパフォーマンスの魅力があると思いますが、ラムコさんが思う「lilbesh ramko のライブの魅力」とは何でしょうか。
いろいろありますが、特に意識しているのは「発散」ですね。普段生活では絶対出しちゃいけない声と声量を思い切り出せるから、それが気持ちいいなって思います。
「非日常的な体験」ですね。
そうです。
ライブで一番盛り上がる曲は「lost woods!」だと言われていますが、もし「これだけは聴いてほしい」曲があれば一つ挙げていただけますか。
「i (dont) know.」っていう曲は歌いやすい曲だと思うので、みんなで歌えたら嬉しいなって思います。
では、最後に一言お願いします。
2月22日に初めて韓国に行くので、物凄くワクワクしてます。ご飯も大好きだし、行きたい国だったので、皆さんと会えるのを本当に楽しみにしております。全力で楽しませるので、何卒よろしくお願いします!
Azure Vol.1
日付: 2025年 2月 22日
場所: @BRST STUDIO Hongdae
内容: https://x.com/presents_azure/status/1881990795408146821